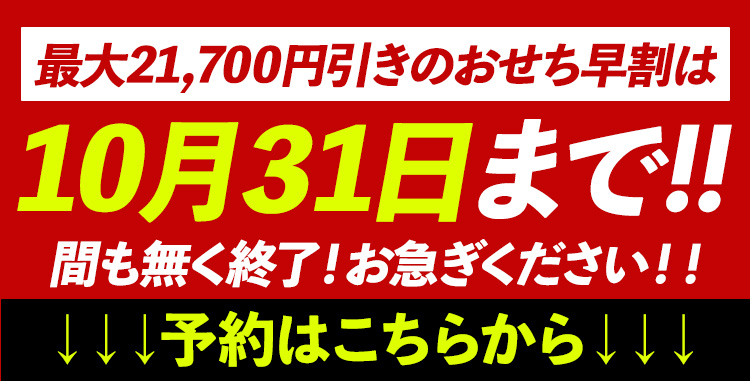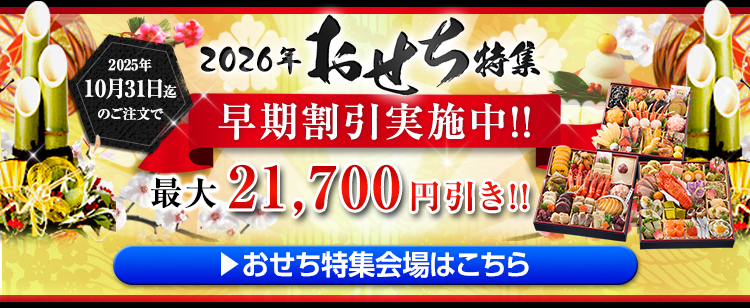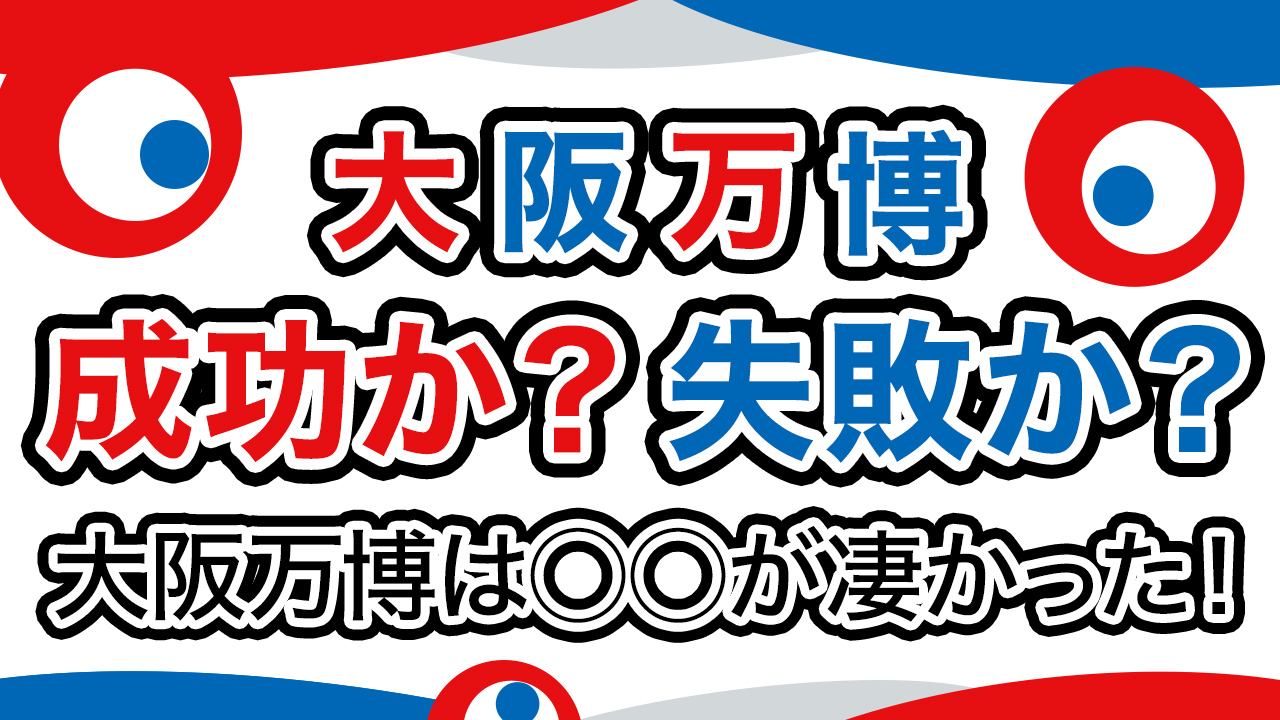
皆さんこんにちは!匠本舗スタッフのひぐちです!
大阪・関西万博は、目標来場者数(実質2,558万人)が想定(2,820万人)に届かず、「失敗」という声も一部で上がりました。
しかし、その評価は公平ではありません。関西万博は、次の二重の厳しい制約の中で運営されました。
- 【物理的制約】近年の万博と比較して会場面積が大幅に狭い(会場の狭さ)
- 【運営的制約】混雑緩和のために日時指定の入場予約システムを原則必須とした(集客の自己制限)
この記事では、これらの制約を乗り越え、関西万博が近年の国際博覧会と比較して、いかに効率的で価値ある成功モデルであったかを、客観的なデータに基づいてわかりやすく分析します。
それではいってみましょう!
この記事はこんな人にオススメ!
- 「関西万博は失敗だった」という意見に納得できない人
- 万博の評価を客観的なデータ(面積あたり来場者数など)で知りたい人
- 狭い会場や入場予約という制約の中で、万博がどれだけ効率的だったかを知りたい人
関西万博の「実質入場者数」を改めて確認!

まず、最終的な来場者数の数字を正しく理解しましょう。万博協会が公表する総来場者数には、「AD証入場者(関係者)」が含まれるため、一般のチケットによる「実質入場者数」に注目することが重要です。
| 来場者数区分 | 最終来場者数(万人) | 備考 |
|---|---|---|
| 総来場者数 | 2,902 | AD証(関係者 約344万人)を含めた人数。万博協会の「目標2,820万人」は達成。 |
| 実質入場者数 | 2,558 | AD証入場者を差し引いた、一般のチケットによる入場者数。目標は未達。 |
出典:2025年日本国際博覧会協会発表(2025年10月14日、報道ベース)
実質入場者数(2,558万人)は目標を下回りましたが、この数字が「狭い会場」という物理的制約の中でどれだけ優れていたのかを、次の章で世界の万博と比較しながら見ていきましょう。
万博の「成功」を測るカギは「会場の狭さ」

国際博覧会の集客力を比較する上で、会場面積は非常に重要な要素です。会場が狭ければ、安全上の理由から1日の最大収容人数が制限されるため、物理的に総来場者数に限界が生じます。
近年の万博会場面積ランキング:関西万博は「最も狭い」部類
近年の主要な国際博覧会と、関西万博の会場面積を比較してみます。
| 万博名称 | 開催年 | 会場面積 (ha) | 面積の比較 |
|---|---|---|---|
| 上海国際博覧会 | 2010年 | 523 | 最大規模 |
| ドバイ国際博覧会 | 2020年(2021年実施) | 438 | 2番目に広い |
| 愛・地球博(愛知) | 2005年 | 185 | |
| 大阪・関西万博 | 2025年 | 155 | 近年の主要万博で最も狭い部類 |
| ミラノ国際博覧会 | 2015年 | 110 |
関西万博の会場面積155haは、ドバイ万博(438ha)と比べると約3分の1強しかありません。つまり、物理的に「集客の絶対数」で比較するのは、公平ではないことがわかります。
実質来場者数ランキング:狭い会場でドバイ万博超えを達成!
会場が狭いという不利な条件にもかかわらず、関西万博は驚異的な集客力を発揮しました。
| 順位 | 万博名称 | 開催年 | 実質来場者数(万人) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 上海国際博覧会 | 2010年 | 7,308 |
| 2位 | 日本万国博覧会(大阪) | 1970年 | 6,422 |
| 3位 | 大阪・関西万博 | 2025年 | 2,558 |
| 4位 | ドバイ国際博覧会 | 2020年(2021年実施) | 2,410 |
会場が約3分の1強の広さしかないにも関わらず、関西万博はドバイ万博(2,410万人)を超える実質入場者数を記録しました。この事実は、関西万博の潜在的な集客力の高さと、会期後半の追い上げの凄まじさを証明しています。
「1haあたりの来場者数」で見る驚異の運営効率
万博の「真の成功」を測る最も客観的な指標は、「会場の面積」という物理的制約を考慮に入れた運営効率です。これが「1ヘクタール(ha)あたりの来場者数」です。
会場面積に対する来場者数の比較(効率性ランキング)
会場の広さ(ha)で実質来場者数(万人)を割ることで、「いかに効率よく集客できたか」がわかります。
| 万博名称 | 会場面積 (ha) | 実質来場者数 (万人) | 1haあたりの来場者数 (万人) |
|---|---|---|---|
| ミラノ国際博覧会 | 110 | 2,151 | 19.55 |
| 大阪・関西万博 | 155 | 2,558 | 16.50 |
| 上海国際博覧会 | 523 | 7,308 | 13.97 |
| ドバイ国際博覧会 | 438 | 2,410 | 5.50 |
関西万博の1haあたりの来場者数16.50万人は、ドバイ万博(5.50万人)の約3倍、上海万博(13.97万人)をも上回る、超高効率な集客実績です。
これは、「狭い会場」というハンデを負いながらも、徹底した運営努力と日本の高い関心度によって、面積あたりの密度を極限まで高めたことを示しており、運営効率という観点からは間違いなく「大成功」と言えます。
集客を自ら制限した「日時指定入場予約システム」

関西万博の評価を語る上で、もう一つの大きな制約が、「日時指定入場予約システム」です。
前例の少ない入場制限:コロナ禍のドバイ万博に続く試み
従来の国際博覧会は基本的に「自由入場」が主流でした。しかし、関西万博は「並ばない万博」「安全な万博」を目指すため、入場そのものに日時指定の予約を原則必須としました(先行してこのシステムを導入したのは、コロナ禍で実施されたドバイ万博)。
このシステムは、来場者体験の向上と混雑緩和を目的としましたが、その反面、1日あたりの入場者数に上限を設けることになり、集客を自ら制限する形となりました。実際、最も混雑した日でも、1日の入場者数は24万人前後が限界とされていました。
入場予約の複雑さが初期の集客に与えた影響
システム導入の初期段階では、万博IDの取得、チケットのアクティベート(日時指定)、パビリオンの抽選予約など、プロセスが複雑で「チケットを買うのが面倒」という声や批判も一部で見られました。
開催当初のネガティブな報道や連日の酷暑、そしてこの予約システムの複雑さが重なり、入場者数は前半に伸び悩みました(1日10万人前後)。
しかし、会期後半には、「ミャクミャク」を筆頭とした話題性の高まりと、閉幕を惜しむ駆け込み需要が相まって、連日20万人を超える入場者数を達成しました。入場制限という困難な条件下で、来場者数の目標に迫る高い実績を上げたことは、運営の知恵と努力の賜物と言えるでしょう。
「ミャクミャク」グッズの大ヒットと会期後の経済効果

入場者数が当初伸び悩む中、状況を大きく変えたのが、公式キャラクター「ミャクミャク」です。
単なる記念品に留まらない「ミャクミャク」効果
- ミャクミャク関連グッズは記録的な売上を達成し、連日オフィシャルストアに長蛇の列ができ、品切れが続出しました。
- 当初、賛否両論あった個性的なデザインが、SNSでの大人気と相まって、「可愛くて面白い」という確固たる地位を築きました。
万博協会は、会期終了後も一部の会場外オフィシャルストアやオンラインストアでのグッズ販売を継続することを決定。これは、ミャクミャクが単なる万博の記念品ではなく、キャラクターとして独立したブランド力と需要を持つことを示しています。
これにより、万博の経済効果が会期後も持続するという、異例の成功パターンを生み出しました。
まとめ
大阪・関西万博は、目標入場者数(実質)こそわずかに未達でしたが、その評価は単純な「達成/未達」で判断すべきではありません。
客観的データが示す関西万博の真価
- 【超高効率】「1haあたりの来場者数」は16.50万人を達成。ドバイ万博(5.50万人)や上海万博(13.97万人)を圧倒的に上回る世界トップクラスの効率性を実現しました。
- 【困難な条件】近年の主要万博で最も狭い部類の会場(155ha)と、集客を自ら制限する入場予約システムという二重苦を克服しました。
- 【持続的な効果】「ミャクミャク」グッズの爆発的ヒットにより、会期終了後も経済効果を持続させるという新たなレガシーを残しました。
これらの事実から、大阪・関西万博は、「物理的な狭さ」と「運営上の自己制限」という困難な条件下で、最大限の集客効率と話題性を生み出し、安全・安心を優先しながら最大の成果を導き出した、新しい時代の国際博覧会の成功モデルであったと、自信を持って結論づけることができます。