かつては「下魚」と呼ばれたニシンが、再び脚光を浴びる理由とは?
近年、日本の食卓で再び注目されている魚、「ニシン」

ニシンといえば、かつては「庶民の魚」「下魚(げぎょ)」と呼ばれ、安価で日常的に食べられる存在でした
特に、明治〜昭和初期にかけては、干物や身欠きニシンとして庶民の台所を支えていたようです。
しかし現在、ニシンの評価が再び高まり、人気が急上昇しています。
本記事では、なぜニシンが見直されているのか?
その背景と理由をわかりやすく解説します。
健康志向と相性の良い「栄養価の高い魚」
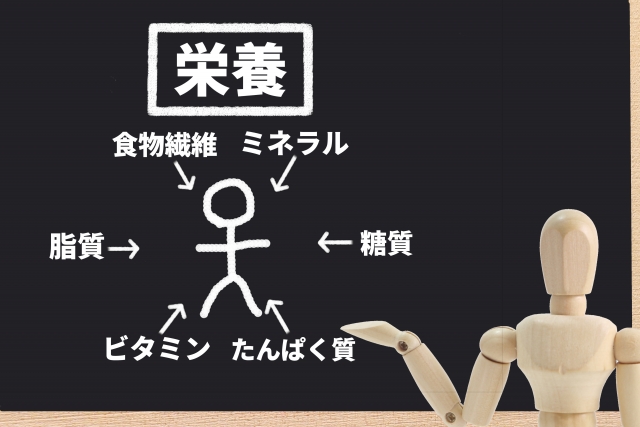
ニシンは栄養を豊富に含み、現代の健康志向に合致しています。
-
オメガ3脂肪酸(EPA/DHA)やビタミンB群、カルシウム、鉄分などが豊富
-
血液循環改善や脳の健康維持に効果的
- 高タンパク・低糖質でダイエット中の食事にも◎
こうした栄養面での魅力が、かつての「下魚」というイメージを覆し、“健康食材”としての再評価に繋がっています。
加工品としての需要拡大

ニシンは鮮魚としての流通よりも、加工品としての活用が非常に多い魚です。
-
身欠きニシンや甘露煮は保存食として通年需要あり
-
近年は缶詰や冷凍食品でも人気
- 数の子(卵)はお正月の定番
調理の手間が少ない加工品は、忙しい現代人の生活にもフィットしています。
なお・・・「世界一臭い」と言われるあの缶詰
あの缶詰も原料はニシンですね・・・
やはり臭くて美味しくないんじゃ?と思われるかもしれませんが
全然そんな事ありません。
ニシンが美味しくなった!?

近年北海道で漁獲されるニシンは、脂の乗りが良くなり
美味しさが増していると評価されています。
-
流通と冷凍技術の改善による鮮度の維持
-
漁獲量の回復と選別の向上
- 資源管理と放流事業の成果
現在の北海道産ニシンは脂の乗りが良く、味わい深いと評価されています。
特に、刺身や焼き物、煮付けなどでその美味しさを堪能できるため人気が高まっています。
漁獲量が回復し、「幻の魚」から復活へ

かつて北海道の主要魚種だったニシンは、1950年代以降
乱獲や海水温の変化により激減し、「幻の魚」とまで言われました。
しかし近年、資源管理の成果が出て、漁獲量が回復傾向にあります。
-
北海道でのニシン漁獲量は2020年で約1万4,000トン(10年前の4倍以上)
-
若魚の保護や漁網の改善により、持続可能な資源利用が進む
ニシンの漁業が再び活気を取り戻したことが、市場での再評価に繋がっています。
まとめ
ご高齢の方だと、「えーニシン?美味しくないでしょ」
というイメージを持たれている方も自身の周りで多いのは事実です。
しかし、ニシンの缶詰を試食すると、意外にも美味しいものが非常に多いです。
皆さんもかつての【下魚】だからと敬遠せず、一度機会があれば食べてみてください。
「庶民の魚」から「未来志向の魚」へ —— ニシンの再評価は、日本の魚食文化の復権を象徴する動きとも言えるでしょう。
おわり。
匠本舗海鮮お買い得情報↓↓
ここまで読んでいただきありがとうございます!
匠本舗では海鮮グルメクーポン祭り開催中です。
在庫が多い商品のセールも随時開催していきますので、ぜひ見て行ってください。
赤字必須のセール情報もメルマガ会員限定配信していますので
会員登録だけでもぜひやってみてください。


