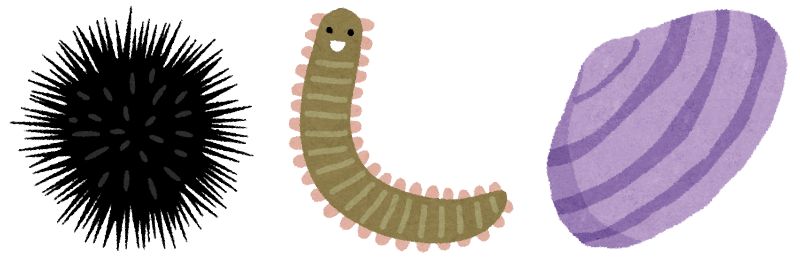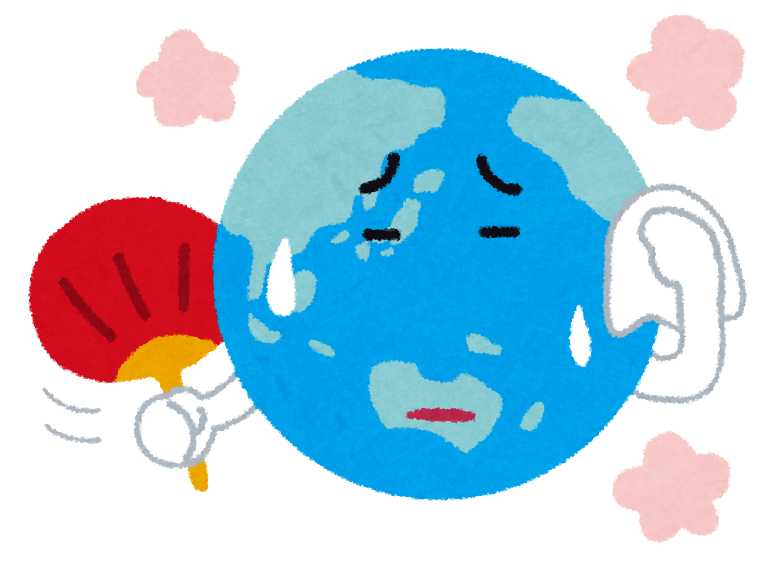年末年始、食卓の主役を張る「カニの王様」、たらばがに!
あのデカくてプリップリの身は最高ですよね!
でも、私たちが「うまいうまい!」と食べているそのカニが、一体どんな場所で、どんな一生を送ってきたのか、想像したことありますか?
「寒い海にいるんでしょ?」くらいのイメージかもしれませんが、その現実は私たちの想像を絶する過酷さなんです…
この記事では、「食べ方」や「見分け方」は一切ナシ!
ただひたすらに、たらばがにの「誕生から死ぬまでの生態」に焦点を当てた、マニアックな5つのポイントをご紹介します!
これを読めば、次たらばがにを食べる時、その一口の「重み」が変わるかもしれませんよ…!
目次
ポイント1:【住んでる世界が過酷すぎ】水温10℃以下!「冷蔵庫」みたいな深海が故郷
まず、彼らが住んでいる「家」からしてヤバいです。
たらばがにが生きていけるのは、水温10℃以下のエリアだけ。
ちょっとでも水が温かいと、もう生きていけません。
しかも、住んでいる場所は水深30m~360mという、太陽の光もあまり届かない冷た~い深海。
水温は0℃~3℃なんて場所もザラ。まさに「冷蔵庫の中」で暮らしているようなものです。
「じゃあ、世界地図でいうとどのへん?」と思いますよね。
彼らの故郷は、ズバリ「北半球の、極寒の海」です!
- メイン会場:「北太平洋」(オホーツク海・ベーリング海)
地図の上の方、日本(北海道)、ロシア、アラスカ(アメリカ)に囲まれた、あのあたりです。世界最大の漁場ですね。 - まさかの飛び地:「北欧」(バレンツ海)
今度は地図をぐーっと左(ヨーロッパ側)へ。ノルウェーやロシアの北の果て、北極海に面した海です。(※ここは昔ロシアが放流したらめちゃくちゃ増えた、「外来種」の産地なんです!)
とにかく、赤道に近い「あったかい海」には絶対にいない、北国のエリートなんです。
ポイント2:【誕生の奇跡】まさに深海の「七夕」!年に一度の恋で子孫を残す
そんな過酷な環境で、どうやって子孫を残すんでしょうか?
彼らの恋愛スタイル、実はめちゃくちゃドラマチックなんです!
なんと、たらばがには普段、オスとメスは別々の場所で生活しています。
水深やエリアを分けて暮らしていて、お互いまったく会うことがありません。
まさに、深海の「彦星」と「織姫」状態!
じゃあ、いつ会うのか?
それは、年に一度の「繁殖期」だけ!
繁殖期になると、オス(彦星)は「織姫」に会うために、メスが集まる場所へと旅に出ます。
そして脱皮直前のメスを見つけると、他のオスに取られないよう、ハサミで優しくガード(交尾前ガード)!(画像元)
無事に「七夕のデート(交尾)」が終わると…
彦星(オス)はさっさと元の生活場所へ帰り、織姫(メス)は「子育て」に入ります。
メスはなんと約10ヶ月~12ヶ月もの間(七夕どころの騒ぎじゃない!)、数万粒の卵をお腹に抱えて守り抜きます。
しかも、卵がちゃんと育つように、わざわざ150m以上の、もーっと冷たい深海へ移動して過ごすんです。まさに命がけ!
春になってようやく孵化した赤ちゃん(ゾエア幼生)は、親とはまったく似ていないエビみたいな姿。
「プランクトン」として、海の中をフワフワと漂う「旅」に出ます。
数万匹の兄弟のうち、無事に海底にたどり着けるのは、ほんの一握り…。誕生からすでにサバイバルです。
ポイント3:【成長の試練】大人になるまで10年!?「脱皮」で命がけの変身
海底にたどり着いても、試練は終わりません。
カニやエビの仲間は、硬い殻を脱ぎ捨てる「脱皮」でしか大きくなれないんです。
この「脱皮」のサイクルも、年齢によって全然違います。
- 若い頃(稚ガニ):まだまだ成長期!「もっとデカく!」と、年に数回も脱皮を繰り返します。
- 大人になってから(成体):体が大きくなると、脱皮も大仕事。頻度は年に1回、あるいはそれ以下にまで減っていきます。
脱皮直後は体がフニャフニャで、敵に襲われたらひとたまりもない、一番無防備な瞬間です。
この命がけの変身を、何度も何度も繰り返して大きくなります。(ちなみに、この時なら失った脚も「再生」できます!)
タラバガニの脱皮する貴重な動画がありました。
でも、一番驚くのはその成長スピード。
たらばがには、本当に成長がゆっくりなんです。
・孵化後6年 → 甲羅の幅がやっと10cmくらい。
・孵化後10年 → ようやく「漁獲サイズ」に仲間入り。
・甲羅の幅20cm超 → ここまで育つのに16年~17年!
私たちが「お、立派なタラバだ!」と感動しているあのカニは、10年、15年と、あの過酷な深海を生き抜いてきた「大先輩」なのかもしれませんね!
ポイント4:【王様の食生活】メインは貝類!「右ハサミ」で砕いて食べる
10年もかけて育つ王様、一体何を食べてるんでしょう?
基本は「雑食性」で、獰猛なハンターです。
そのメインディッシュは、「海底にいる、動きの遅い生き物」たち!
- ゴカイ(ミミズみたいなやつ)
- 二枚貝(アサリとかホタテの仲間)
- ヒトデやウニ、小型の甲殻類など
これらを見つけると、あのデカい「右ハサミ」(パワー担当)で殻ごと「ガシッ!」と砕き、小さい「左ハサミ」(テクニック担当)で器用に中身をつまんで食べています。
水槽の実験では、脱皮のために「甘エビの頭」を殻ごとバリバリ食べたという情報もあるので、硬い殻からカルシウムを摂るのも大好きみたいですね!
…そんな王様も、オオカミウオやミズダコには食べられちゃうことがあります。
さらに「コンニャクウオ」という魚には、甲羅のエラの内側にこっそり卵を産み付けられることも!王様も、知らぬ間に「産卵場所」として利用されちゃってるんです(笑)
ポイント5:【意外な弱点】赤ちゃんは超デリケート!「温暖化」がヤバい
水温0℃でも平気な王様、無敵に見えますが、実は「意外な弱点」があります。
それは、「赤ちゃん(幼生)時代」のデリケートさです。
大人のカニは低温にめちゃくちゃ強い体を持っていますが、生まれたてのプランクトン時代は、まだその能力が備わっていません。
だから、ちょっとした水温の変化や、海水の酸素が薄くなる(低酸素)状態に、ものすごく弱いんです。
ここで「地球温暖化」が関係してきます。
もし海の温暖化が進んで、卵を抱えたメス(織姫)が、卵を育てるのに最適な「超・冷たい深海」を見つけられなくなったら…?
卵が変な時期に孵化してしまったり、水温ストレスで赤ちゃん(幼生)が大量に死んでしまう可能性があります。
私たちが獲るカニが減っている背景には、獲りすぎだけでなく、こうした「温暖化による生態系の異変」も大きく影響しているかもしれないんです。
まとめ:その一口は「10年」のドラマ!
たらばがにの過酷すぎる「私生活」、いかがでしたか?
「5つのポイント」をおさらいしましょう!
- 水温10℃以下の「冷蔵庫」みたいな北の海で暮らしている。
- 年に一度だけ会う「深海の七夕」スタイルで子孫を残す。
- 命がけの「脱皮」を繰り返し、大人(漁獲サイズ)になるまで「10年」もかかる。
- メインディッシュは「貝類」。右ハサミで砕いて食べる。
- 赤ちゃんは超デリケートで、温暖化のせいでピンチかも。
私たちが「プリップリでうまい!」と食べているあの脚の身は、たらばがにが10年という長い歳月を、過酷な深海で生き抜いてきた「証」そのものなんです。
そう思うと、なんだか一口の味が、いつもよりずっと深く感じられませんか?
次にたらばがにを食べる時は、ぜひこの「10年のドラマ」に思いを馳せてみてくださいね!
【特別ご案内】おすすめ「超特大たらば」で決まり!
カニ特集やってます!
ここまで読むと、もうタラバガニが食べたくなってきますよね!?
そんなあなたに、とっておきの商品をご紹介します!
\ 圧倒的存在感! /
プレミアム超特大9Lボイルたらば半むき身満足セット1.8kg超(総重量約2.1kg)
特大サイズの9Lボイルたらばが、なんと1.8kg超(総重量約2.1kg)の大ボリューム!
半むき身だから、調理もラクラク。届いてすぐに、あのプリップリの身を存分にお楽しみいただけます。
家族みんなで囲む食卓はもちろん、贅沢なひとりカニパにも最適!
今年の冬は、この超特大たらばがにで、最高の思い出を作りませんか?
ビールや日本酒との相性も抜群!
ジューシーなカニの旨みが、お酒の味わいを一層引き立てます。
この圧倒的な身入り!
食べ応え満点のタラバガニで、極上の食体験をお届けします。