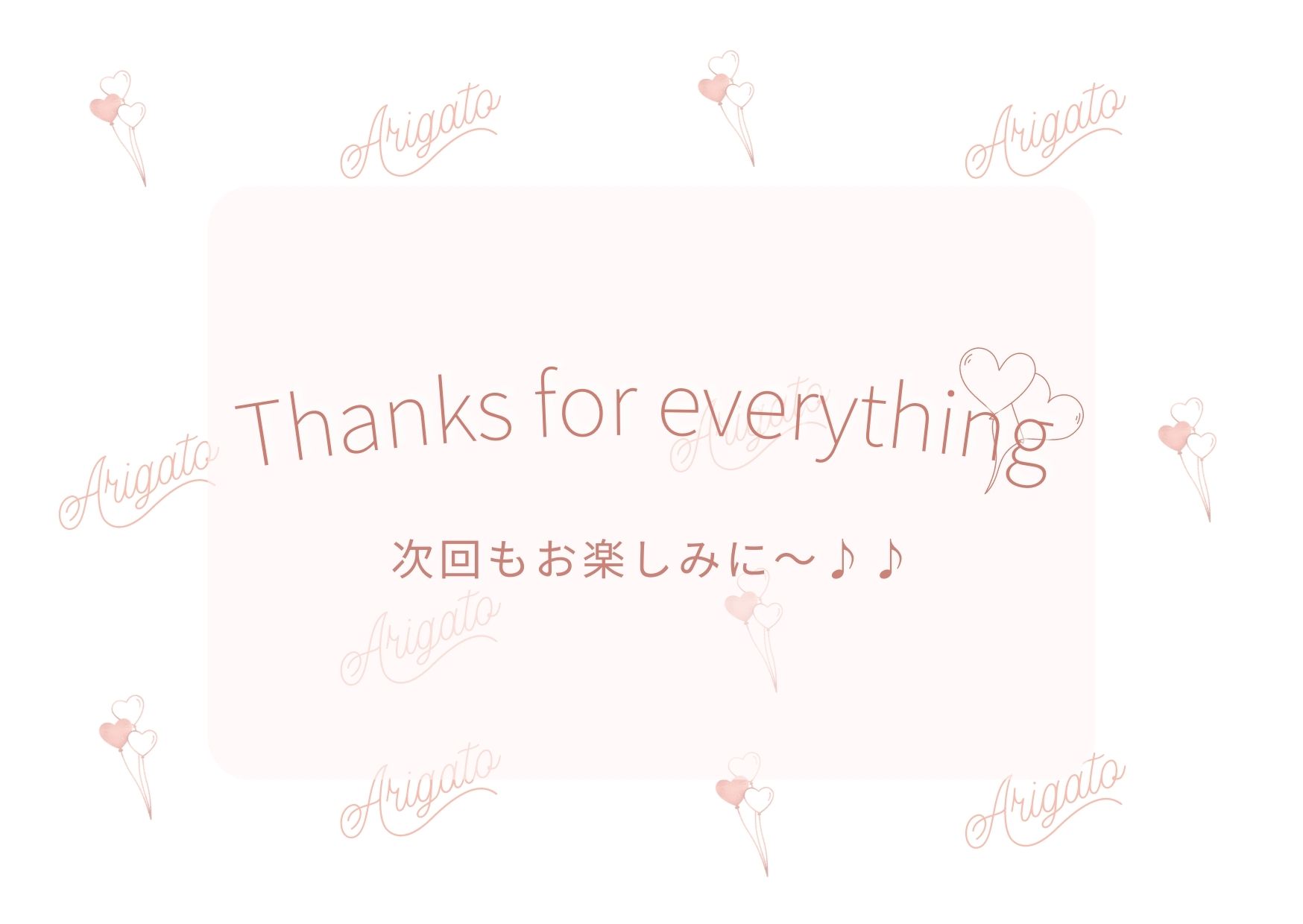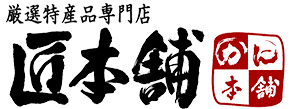みなさんこんにちは(^^)/
スタバに1日の活力をもらってる西川です!!
「なんだか最近、愛犬の元気がない」
「ご飯を残すことが増えた気がする」
そんな飼い主さんの声が増えるのが、
ちょうどGW明けの今の時期。
実は、犬にも人間と似たような「五月病」のような
状態が見られることもあります。

この記事では、犬の五月病に見られる症状や原因、
飼い主ができる対策・予防法についてわかりやすく解説します!
・犬の五月病とは?
「五月病」とは、本来は人間に使われる言葉。
特に新社会人や新入生が4月の環境の変化に適応できず、
5月に入ってから心身に不調をきたす状態を指す。
犬の場合にも、春から初夏にかけての「気温の急変」や
「生活リズムの変化」「環境のストレス」によって、
似たような症状が現れることがあります。
医学的には「五月病」という病名はありませんが、
飼い主にとっては注意したい季節性の不調のひとつです🍀
・犬の五月病の主な症状
「食欲不振」
いつものフードを残したり、食いつきが悪くなったりする
「散歩を嫌がる」
外出を避けるようになったり、歩く速度が遅くなる
「過剰睡眠」
日中もぐったりして寝ている事が増える
「元気がない」
反応が鈍かったり、遊びに興味を示さない
「トイレの失敗」
普段しない場所で粗相をしてしまう
「攻撃的になる」
急に吠えたり、触られるのを嫌がる
軽度であれば数日から1週間ほどで自然に回復する場合もありますが、
長引いたり悪化するようであれば早めに動物病院を受診しましょう🍀
・犬が五月病になる原因
①季節の変化
春から初夏にかけては、日中の気温が急に高くなることがあります。
特に寒暖差が激しい年は、犬の体温調節にも大きな負担がかかります。
②飼い主との接触時間の変化
GW中は飼い主と過ごす時間が増え、
たくさん遊んだりお出かけしたりと刺激が多い日が続きますが、
その後急に日常生活に戻ることで、犬が寂しさやストレスを感じることがあります。
③環境や生活リズムの乱れ
引っ越し、新しい家族(赤ちゃんやペット)が増えるなど、
春は人間側の生活も変化しがち。
それに伴い、犬の生活リズムが乱れると、心身のバランスを崩すことがあります。
・犬の五月病への対処法
①規則正しい生活リズムを整える
毎日同じ時間に食事・散歩・就寝をすることで
犬の生活サイクルを安定させましょう。
不安定なリズムはストレスの原因になります。
②快適な室内環境を作る
22℃~25℃程度、湿度40%~60%前後を保ち
犬にとって快適な居場所を用意して、換気をこまめにおこないましょう。
③スキンシップと遊びでリラックス
おもちゃで遊んだり、優しく撫でたりと、飼い主と触れ合いを通じて
安心感を与えることも大切です。
過度に構いすぎるのは逆効果になる可能性もあるためやめましょう。
④症状が続く場合は動物病院を受診
食欲不振や元気のなさが1週間以上続く場合、
内臓系の病気やホルモンバランスの乱れなど、
別の病気が隠れている可能性がありますので
放置せずに早めに動物病院を受診しましょう。
・犬の五月病を予防するには?
【予防の基本:安定した生活環境を保つこと】
・季節ごとの健康管理(ブラッシングや体温・呼吸の観察など)
・留守番の時間が増える前に徐々に慣らしておく
・無理な外出や予定をいれず、ゆとりのある生活スケジュールにする
犬種によっても機構の変化に弱いタイプもいます。
フレブルやパグのような短頭種は特に注意が必要です!
まとめ
犬の「五月病」も気づいてあげることが大事!
犬の五月病は医学的な診断名ではありませんが、
実際に多くの飼い主が「春~初夏にかけて愛犬の様子がいつもと違う」
と感じています。犬は言葉で不調を訴えることができません。
飼い主が日々の様子をよく観察し、ちょっとした変化にも
気づいてあげることが大切です。
「もしかして五月病かな?」と思ったら
まずは生活リズムや環境の見直しから始めてみましょう。
愛犬との快適な暮らしを守るために
飼い主のケアが何よりのサポートになります(*´ω`*)