
いよいよ今年ももうすぐ終わり。
お正月には「おせち料理」が欠かせないですよね。
よく“おせちは味が濃いから苦手”
“子供があまり食べるものがない”と言われがちですが、
そもそもおせちはどうして味が濃いのでしょうか?
今回は「おせち料理はなぜ味が濃いのか」
についておせち通販の「匠本舗」が徹底解説!
一年に一回のおせち料理がもっと楽しくなるはず![]()
それではどうぞ!
おせちはなぜ味が濃い?という謎について
もちろん、きちんと理由があります。
●保存性を高めるため

おせちの始まりは弥生時代に遡るともいわれ、
季節の変わり目である
「節」にいただく料理として発展してきました。
さらに、冷蔵技術が発展していない時代に、
年末年始に調理をしなくてもよいように
保存性を高めることを目的とし
砂糖や醤油、塩などを多く使用することで
細菌の繁殖を抑える効果が期待されました。
また酢や塩、砂糖を用いた調理法は
食材を長持ちさせる伝統的な知恵からです。
●特別感を演出するため

おせちはお祝いの料理として、
豪華さや特別感を演出するために
特別な味付けが好まれたとも言われています。
また、お酒を飲む機会も多いので
濃い味付けはお酒にも合うと、
宴席に華を添える役割もあります。
●少量を少しずつ、重箱の盛り付けに最適

おせち料理は家族や親戚と囲むことが多いです。
また黒豆や田作りなど、多くの縁起物が
お重箱に入っているというのが基本のスタイル。
そのように“色々な食材を少しずつ食べる”料理だからこそ
少しの量でも満足感を得られるよう
味付けを濃くしていると言われています。
●冷たいままでも味を感じられるように
“正月三が日は火を使わない”という
伝統に基づいたおせち料理は
基本的に冷たいまま食べることが多いです。
したがって、味を濃くして、風味を豊かに
冷たくてもおいしさを感じられるように
味付けを工夫しています。
また、匠本舗のおせちの一部には、
お品書きに「温」マークをつけて
温めたらおいしい料理を表示しています。
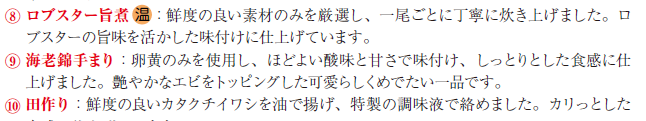
お魚料理やお肉はやはり温めるとジューシーになり
香りも出てよりおいしくいただけますよ。
以上が「おせち料理は味が濃い」理由でした。
しかし近年の健康志向や、
お年寄り・小さい子供に塩分多めの料理はちょっと…
という方に、匠本舗の薄味おせちをご紹介いたします。
京都東山 料亭「道楽」監修
新玉の息吹(あらたまのいぶき) 
創業390余年の京都の名店監修の
大きめおせちは見栄えも抜群。
京風の薄味で、素材を活かした
料亭監修ならではのおいしさです。
京都岡崎「味ま野」監修
翠柳(すいりゅう)

仕出し屋監修だからできる
“冷めてもおいしい”味付けが楽しめます。
大人から子供までおいしく完食できるよう
まろやかな味付けにこだわっています。
しかも、匠本舗のおせちは
全て冷蔵おせちなので、届いたらすぐ食べられ
解凍の手間がありません。
さらに合成着色料・合成保存料は不使用!
安心して召し上がっていただけます 😀
匠本舗は50種類以上のおせちを扱っています!
ぜひ匠本舗のおせちページをご覧くださいね。
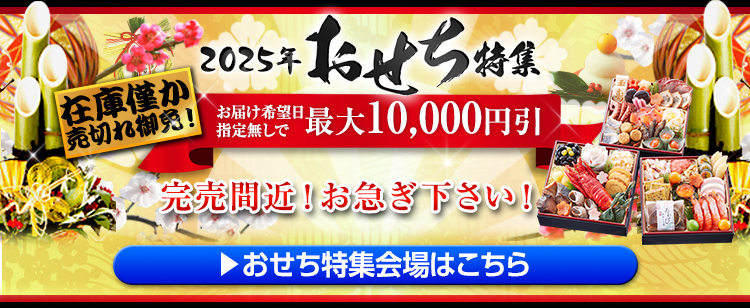
<おせち特集はこちら>
さらに、匠本舗はおせちだけではなく
カニも大変好評をいただいております。
ぜひ、カニ特集もご覧ください!

<かに特集はこちら>
